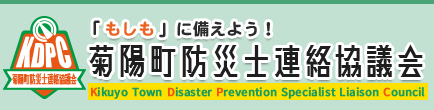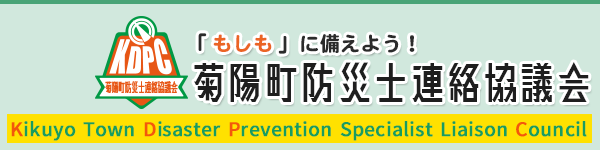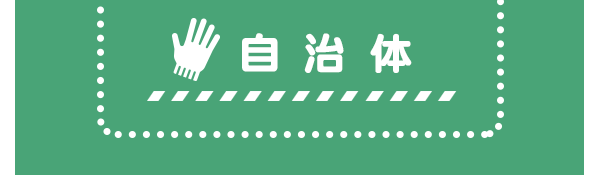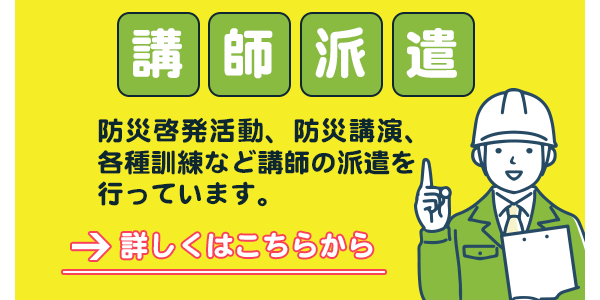防災士とは?
防災士とは、防災に対する知識や技能を持つ人に付与される民間資格で、防災士の資格を付与している日本防災士機構では【自助】【共助】【公助】を原則として、社会のさまざまな場で防災力を高める活動を進めるための十分な意識と一定の知識・技能を習得した人を防災士と定義しています。
防災士基本理念
| 自 助 | 自分の命は自分で守る 自分の安全は自分で守るのが防災の基本です。災害時に自分の身を守るために日頃から身の回りの備えを行い、防災・減災に関する知識と技能を習得し、絶えずスキルアップに努めます。 |
|---|---|
| 共 助 | 地域・職場と助け合い、被害拡大を防ぐ 発災直後における初期消火、避難誘導、避難所開設などを住民自身の手で行うために、地域や職場の人たちと協力して、災害への備えや防災訓練を進めます。 防災士は、そのための声掛け役となり、リーダーシップを発揮します。 |
| 公 助 | 災害時の被害を最小限に抑え、早期の復旧・復興を支援する役割 役場、消防、警察、自衛隊など公的機関による救助・援助のことです。災害時には、公助の役割は、人命救助、避難所の開設、支援物資の提供など、災害対応における重要な役割を担います。 |
防災士に期待される役割
1.平常時の活動
まず自分と家族を守るために、わが家の耐震補強、家具固定、備蓄などを進めます。それを親戚、友人、知人に広めていくとともに、地域・職場での防災啓発、訓練を実施していきます。だれかが積極的に声をかけなければ、人は動きません。 防災士は、まず自分が動き、周囲を動かすよう努めていきます。必要に応じて、防災講演、災害図上訓練、避難所訓練等のリーダー役を果たすとともに、自主防災組織や消防団の活動にも積極的に参加します。

2.災害時の活動
【自分が被災したら】
その場その場で自分の身を守り、避難誘導、初期消火、救出救助活動等に当たります。東日本大震災や熊本地震においても防災士のリーダシップによって住民の命が助かったり、避難所開設がスムーズに運んだという事例が多数報告されています。
その場その場で自分の身を守り、避難誘導、初期消火、救出救助活動等に当たります。東日本大震災や熊本地震においても防災士のリーダシップによって住民の命が助かったり、避難所開設がスムーズに運んだという事例が多数報告されています。
【被災地支援】
近年の災害では防災士による被災地支援活動が積極的に行われています。具体的には避難や復旧・復興に係るボランティア活動あるいは物資の調達・運搬等各種の支援活動に参加し、時には重機を使ったガレキ処理等専門技術を活かした活動も実施されています。

防災士資格までのステップ
STEP1
防災士養成研修講座を受講する
STEP2
防災士資格取得試験に合格する
STEP3
救急救命講習を受講、修了書を取得する
STEP4
防災士認証登録の申請をする